フリーを読んだ。Wired誌の編集長 クリス・アンダーソンの2冊目の本です。2009年7月7日に英語で出版されて、2009年11月21日に日本語版が出版された。NHK出版から速攻出たのが感慨深い。
本の紹介に箇条書きが書かれていた。これは見るとどんな本か分かる。
- デジタルのものは、遅かれ早かれ無料になる
- アトムも無料になりたがるが、力強い足取りではない
- フリーは止まらない
- フリーからもお金儲けはできる
- 市場を再評価する
- ゼロにする
- 遅かれ早かれフリーと競いあうことになる
- ムダを受け入れよう
- フリーは別のものの価値を高める
- 稀少なものではなく、潤沢なものを管理しよう
どんな業界でも無料との競争が待っている。デジタルは生産コストがほぼゼロだからだ。そうなると、どう無料と戦うか、無料からどうお金を生み出すかを考えなければいけない。
僕はデジタルの世界でずっと仕事をしている。いろいろな組織に所属したが、サービスの適正価格を定義するのは難しい。受託制作のコストは、ほとんどが人件費だ。1日いくら、何日だからいくら。という感じだ。
デジタル制作のコストはほとんどが人件費。早く作ればコストは減る。人件費の安い人で作れば安くなる。人件費の安い国で作れば安くなる。
利用者として考えたとき、無料が嬉しい。そして、無料で素晴らしいものが世の中にはある。オープンソースのCMSイベントに参加するのはこういう動機からだ。オープンソースでどうビジネスするか?みんな試行錯誤している。
でも、IT業界はどんどん無料に近づくと確信している。まあ、今は会社では有償の受託サービスを提供しているのだが…。
デジタル制作において、市場に規模の経済は働くか、制作体制には規模の経済は働かないとずっと思っている。人をたくさん集めて、大量生産するようなビジネスではない。さらに、リソースはどんどんクラウド化する。人もクラウド化して、組織の形は変わる。絶対そうなる。
場所に依存するビジネス以外は、同じ場所にいることのメリットは弱くなる。顔が見えてやりやすい。という以上に、適材適所に最適な体制を作れるほうが強い。そういう風に世の中が明らかに変わる中で、どう働くべきかいつも考えます。働き方もビジネスモデルも変わる。10年前と今は全然違う。10年後も違う。
最近は、初期費用を頂くビジネスモデルは破綻していると感じていて、個人的にウェブの相談を受けるとそういう話をさせていただいている。そういうことをやっているときに、この本を読んだから、ああやっぱそうか。と思うことがしばしばありました。興味ある人は読んでみて下さい。
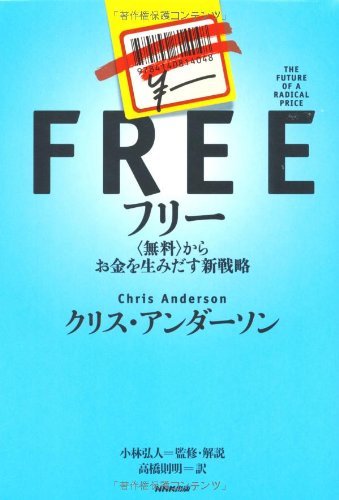

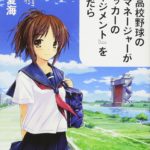
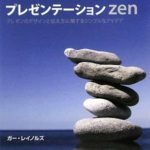
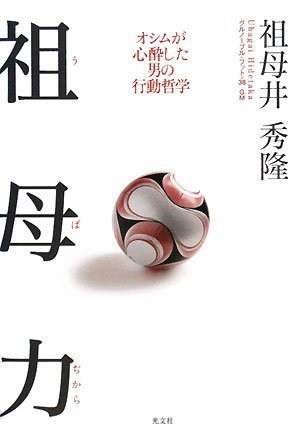
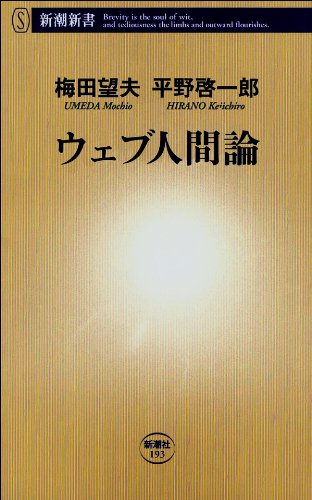
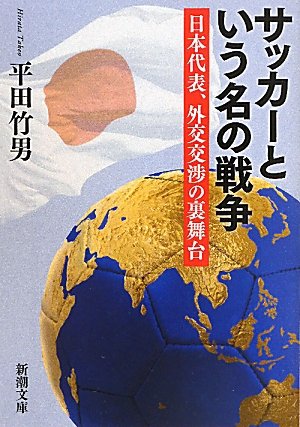
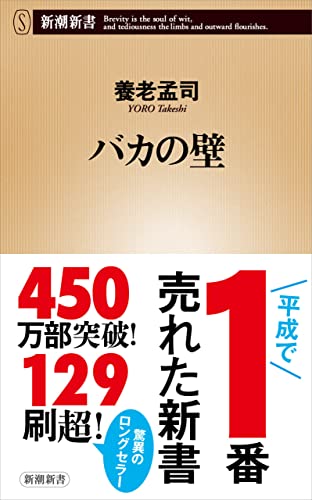
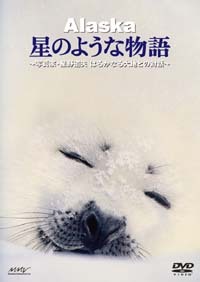

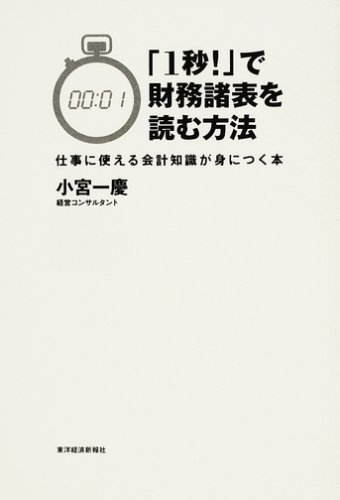
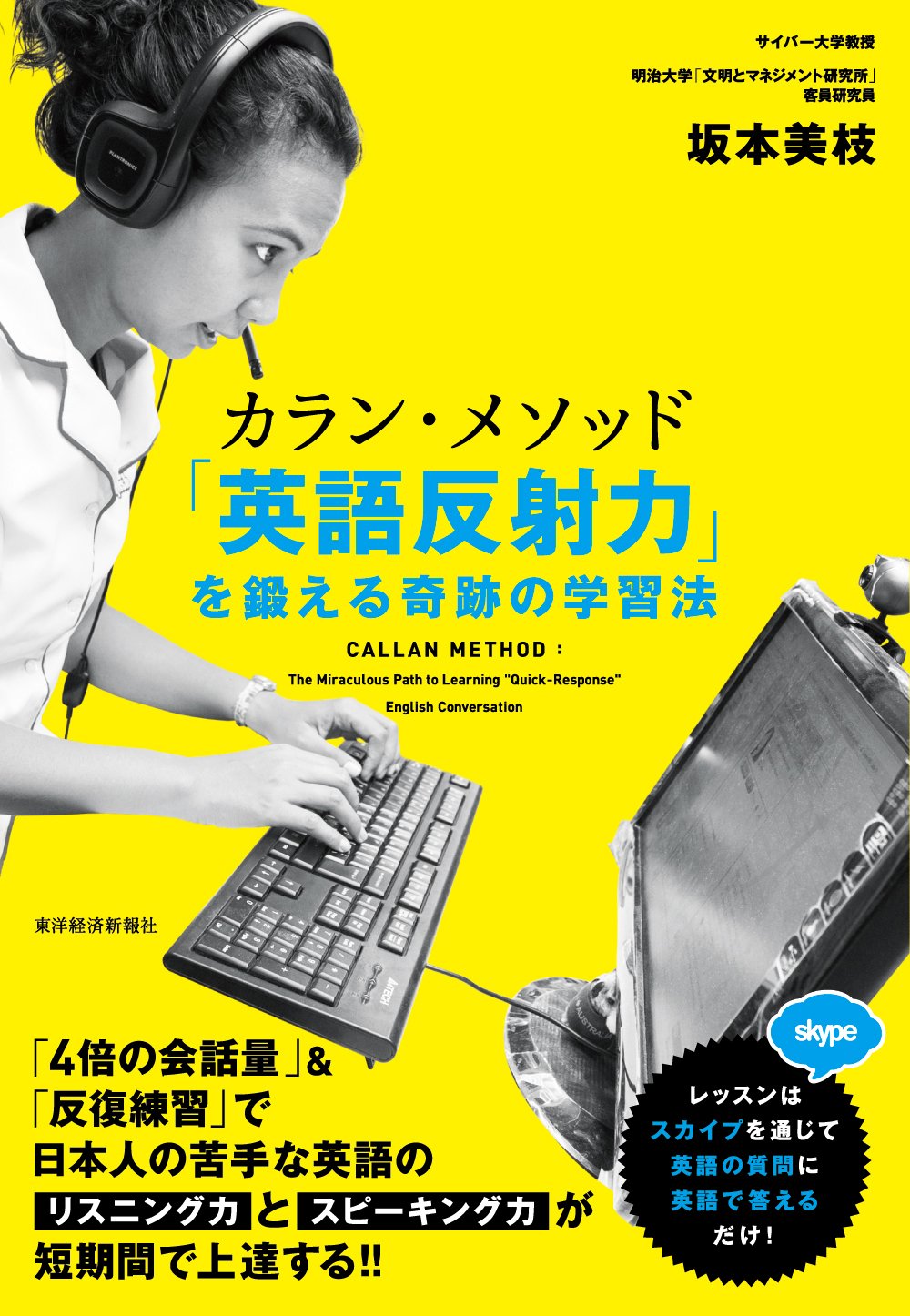















コメントを残す