コロコロPKが代表的なように、遠藤保仁のプレーは落ち着いてる。僕はそれが苦手。小学生の時の通知表に、「落ち着きがない」と書かれていた僕。サッカーも同様で、プレッシャーの中で、落ち着いたプレーをすることが得意でない。
プレッシャーの中で落ち着くというのは、とても難しい。僕のスタイルはたえずハイテンションで走り回って相手を圧倒すること。
自分とは正反対のプレースタイルの選手がどんなことを考えているのか興味深かったのだが、意外にも自分の考え方と共通点があった。
印象深かったのは、「気持ち」と「楽しむこと」を何よりも一番大事だと考えているところ。
そして、自分の子供は、ユースではなく高校サッカーをさせる、と書いてたこと。ユース上がりで、プロで活躍している選手は少ない。というか、ほとんどいない。
ハングリー精神を持ちにくい日本においては、若いうちにクラブ活動のような理不尽なシゴキが必要なんじゃないかと思う。(今のクラブ活動ではそういうのも減ってそうだが。)
先輩に走っとけ!と言われればそれは絶対。理由なんてない。サッカーの実力は関係なく、先に生まれただけで偉い。
ユースだとそんな非合理なことはなく、合理的にサッカーは上手になれるんだと思うが、プロでも社会でも合理的に解決できない壁はある。理不尽な壁を突破するときにはハングリー精神があったほうがいいが、そのマインドはビニールハウスでは育ちにくい。
世の中には理不尽なことがある。満場一致の解は存在しないので、誰かがハッピーなら誰かにそのしわ寄せがくる。それだけのことだ。若いころに理不尽なことや挫折を多少経験しとかないと、大人になって耐えれなかったり、ポキっと折れちゃう気がする。
ジャンプするにはタイミングが重要だが、タイミングをはかるには忍耐が必要。耐え忍んで、忍耐は生まれる。若い人の気持ちを知らんオヤジの意見だけど、これが今の日本を象徴しているような気がする
平等主義、合理主義の教育の弊害
テクニックや知識だけでなく、「気持ち」「楽しむこと」に目を向けて、ダメなことには鉄拳制裁しよう。遠藤は飄々としてるけど、挫折が彼を強くしたように思う。失敗も成功も経験。失敗も成功もしないよりいいですね。
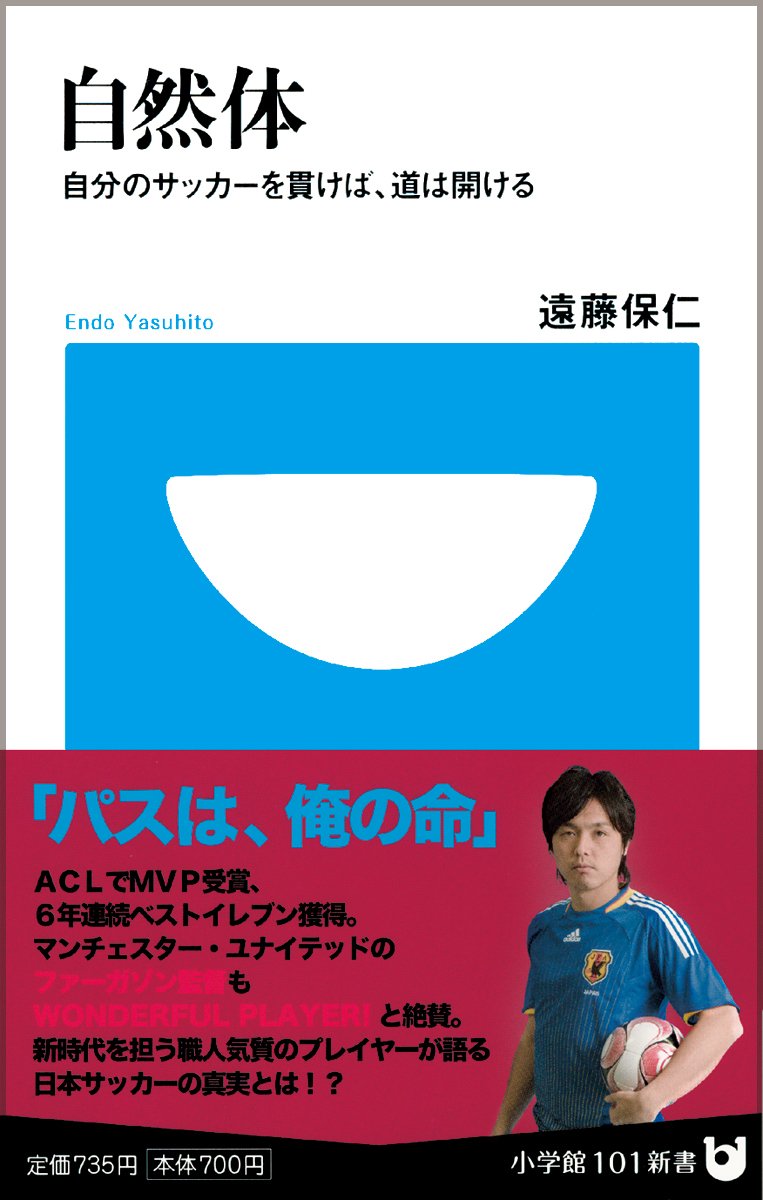

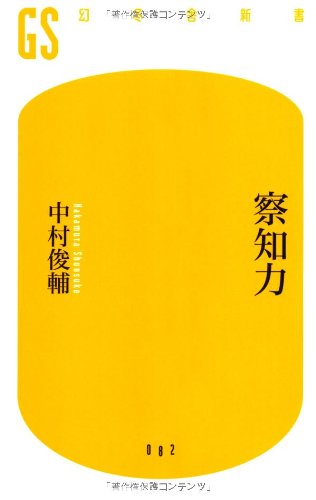
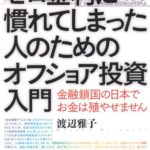
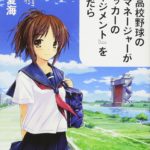
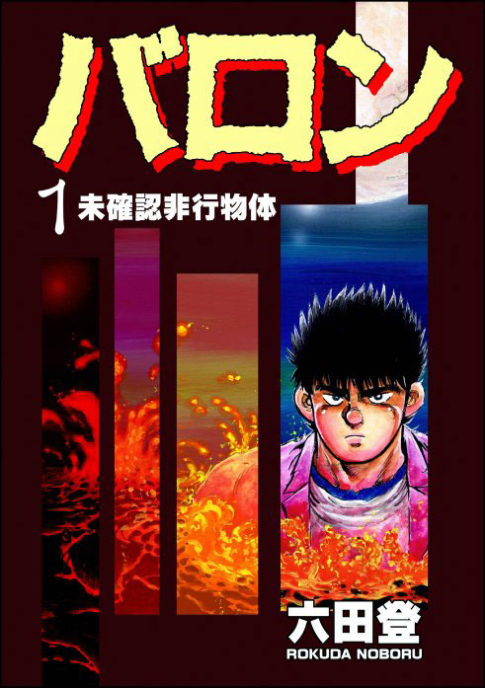
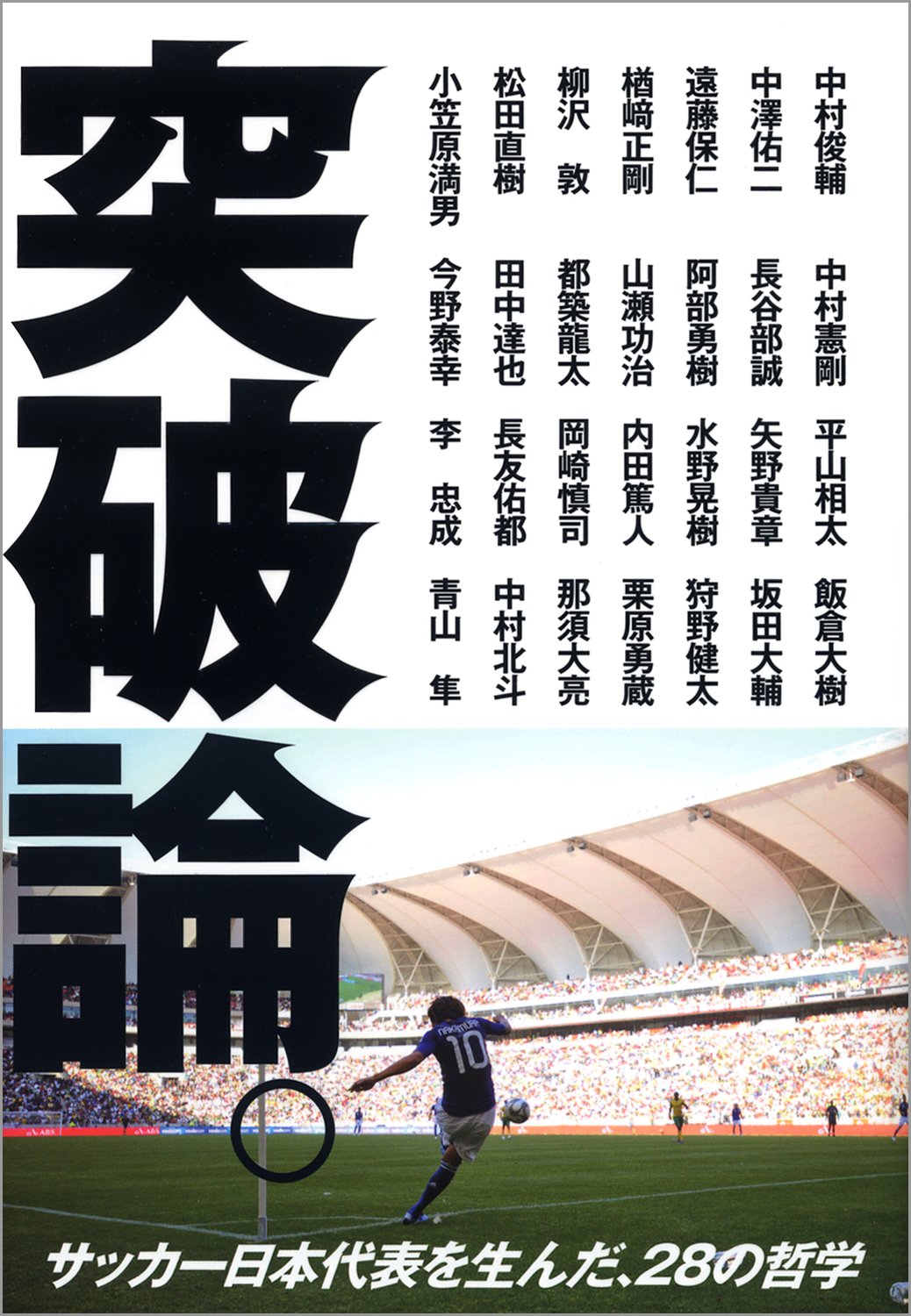
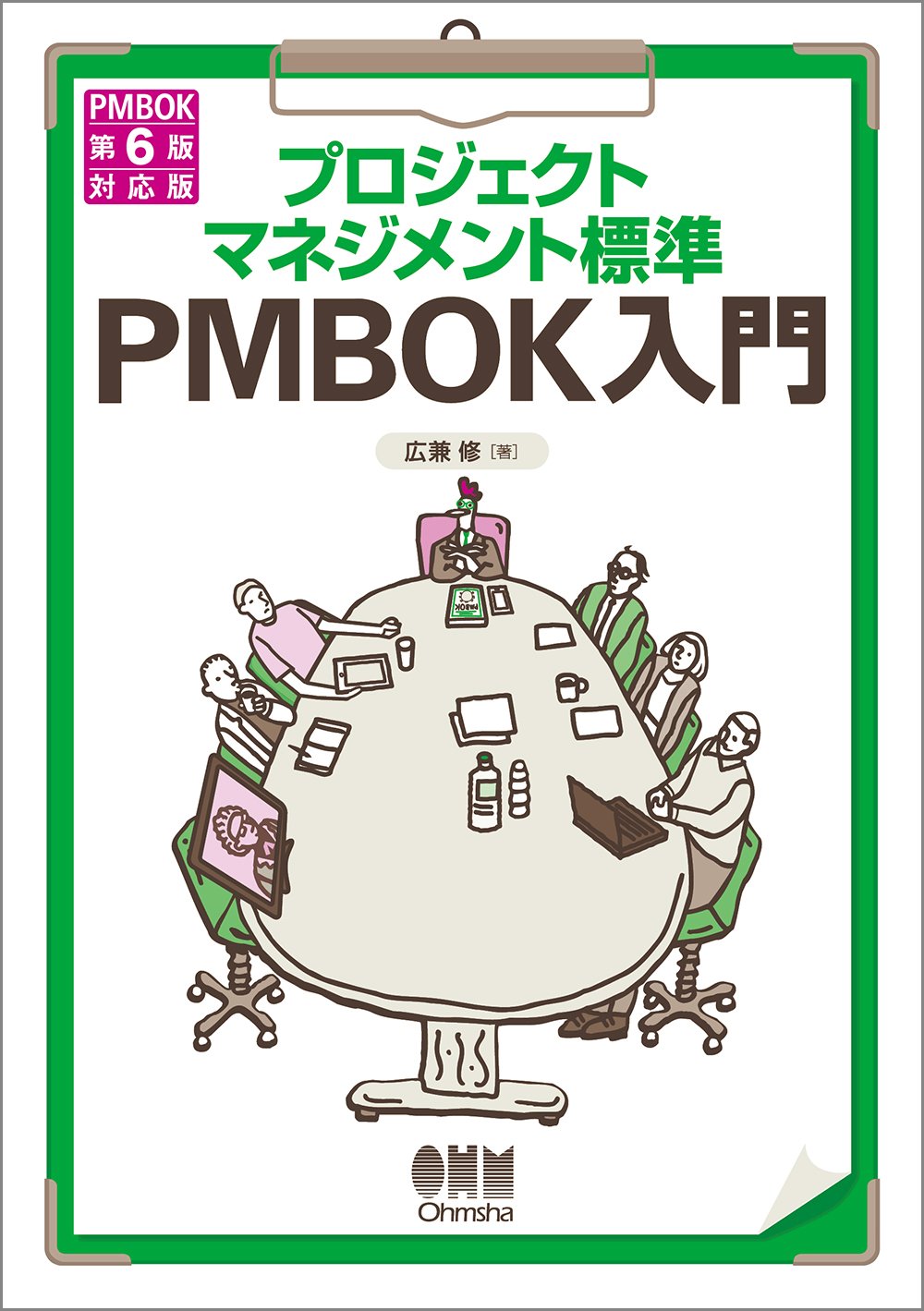
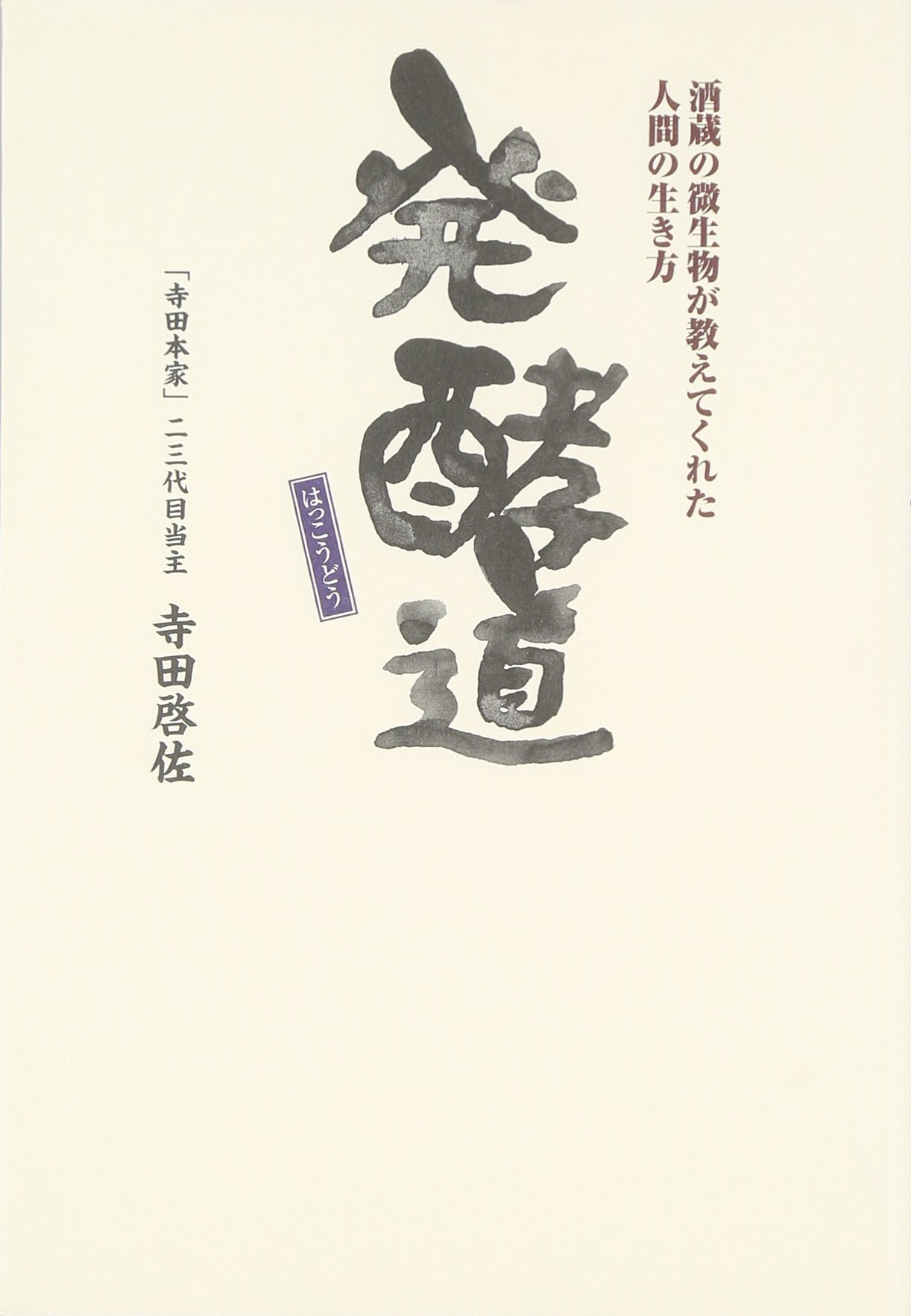
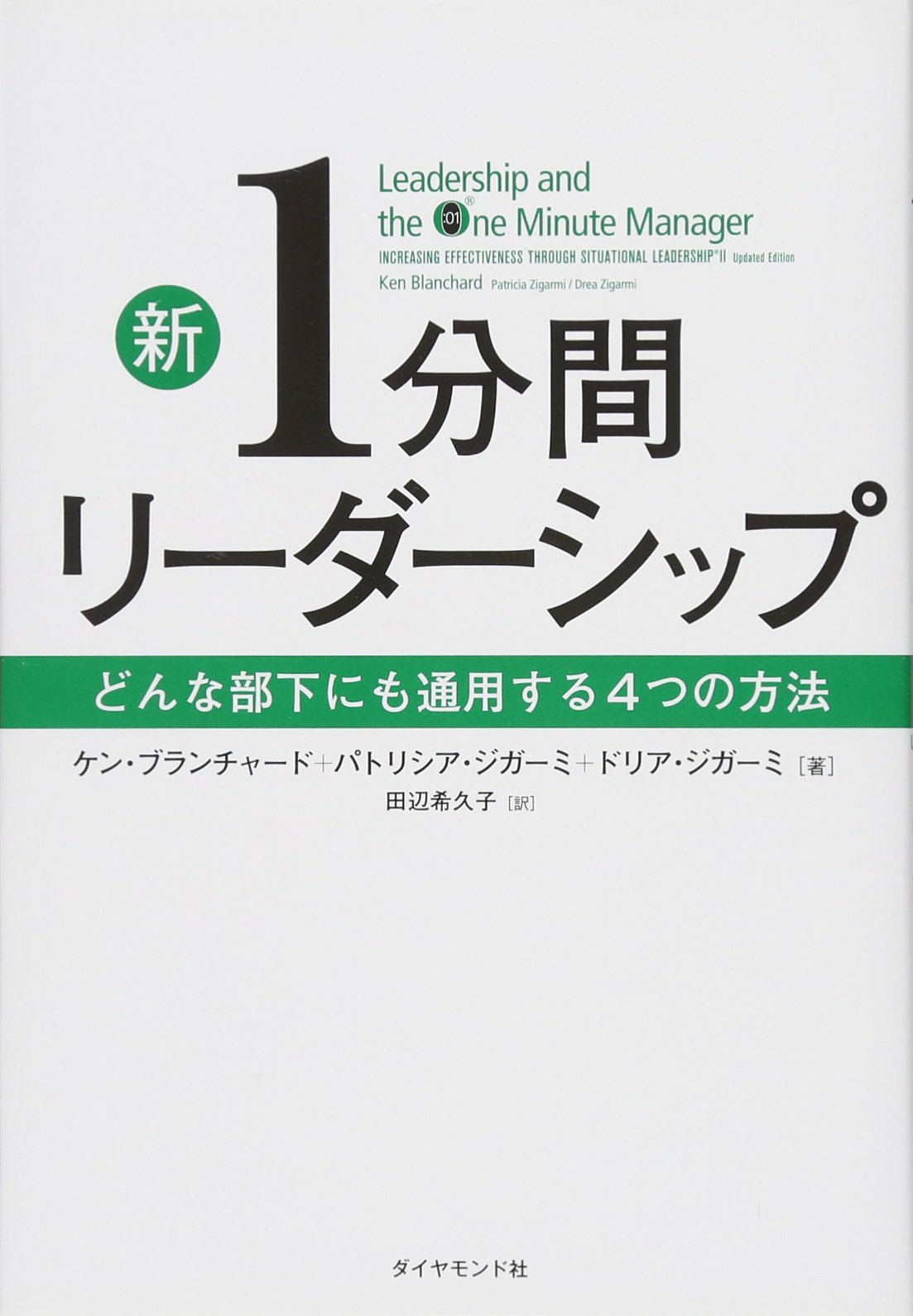
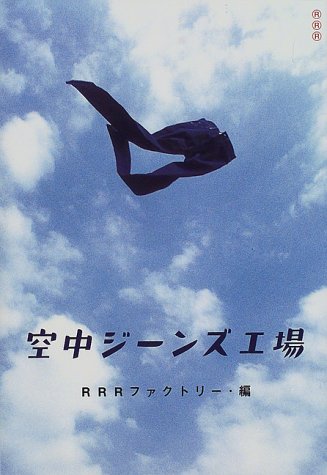
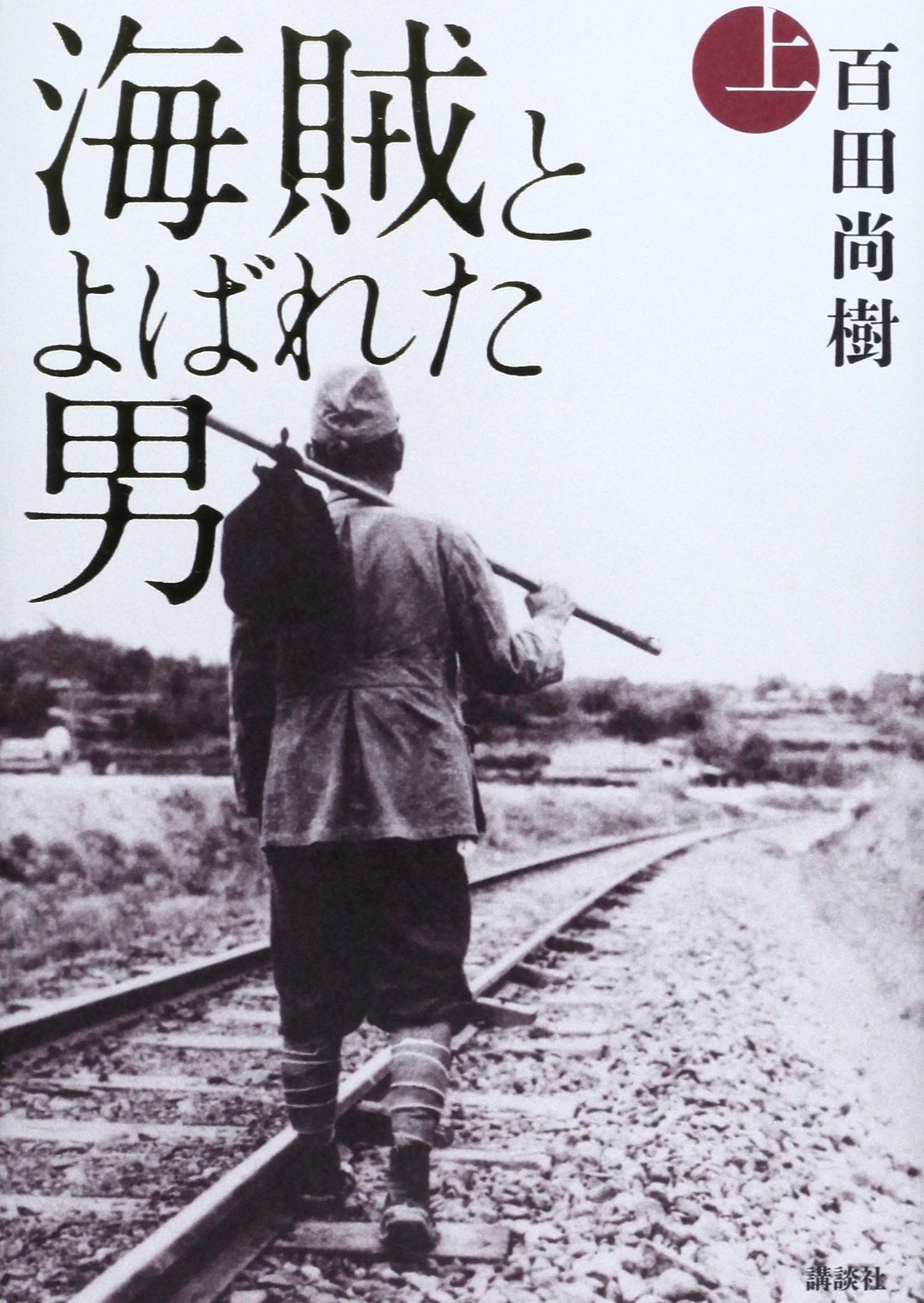
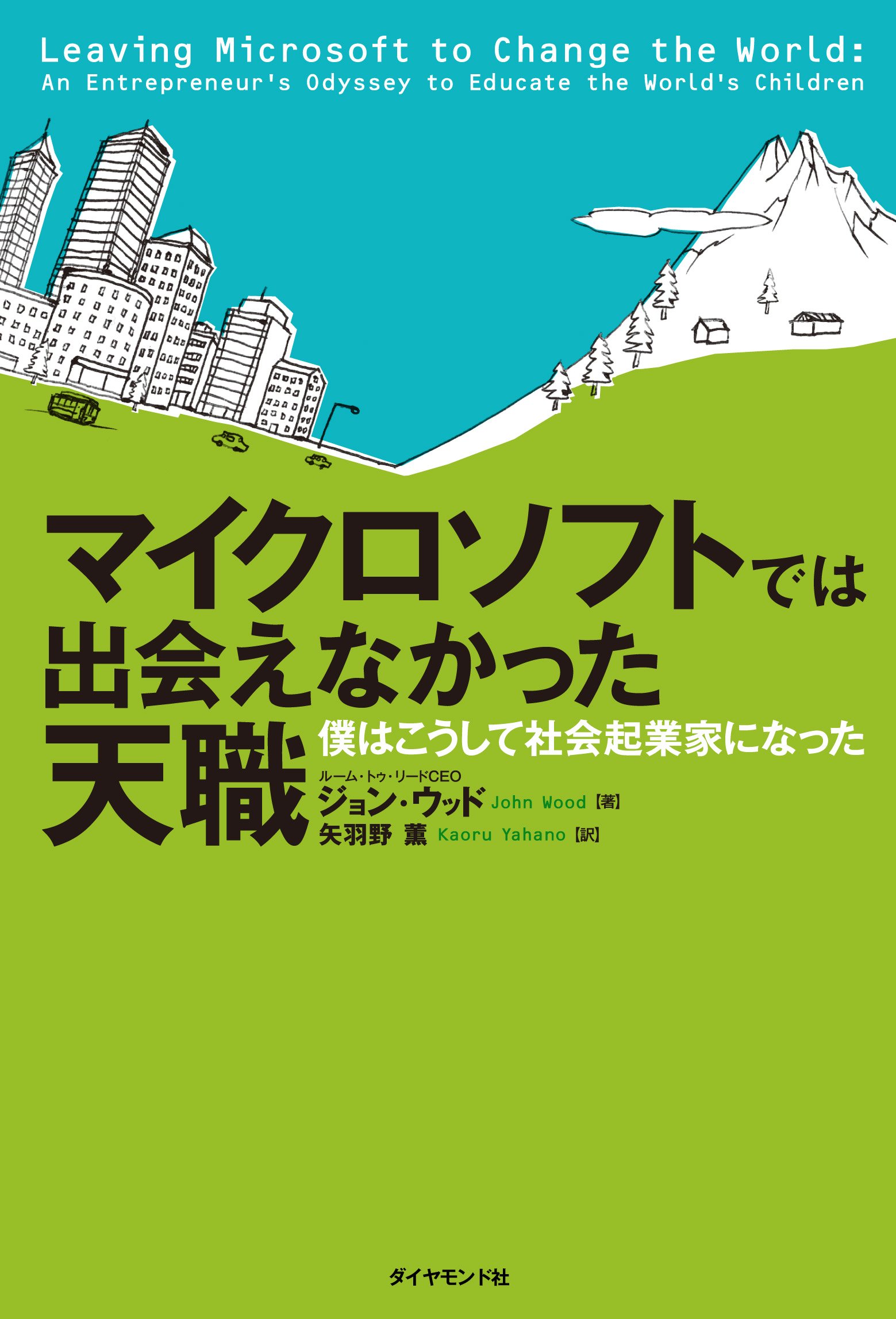















コメントを残す